医師の心電図ブログ、不整脈編の始まりです。
不整脈の解説 全9回
①洞調律 正常洞調律 洞不全症候群
②心房性期外収縮 房室接合部性期外収縮
③発作性上室性頻拍 心房頻拍
④心房粗動 心房細動 偽性心室頻拍(pseud VT)
⑤心室性期外収縮
⑥心室頻拍 TdP torsade de pointes
⑦心室細動
⑧洞房ブロック
⑨房室ブロック
不整脈の1回目は洞性頻脈、洞性徐脈、洞性不整脈についてです。
まず洞調律(sinus rhythm)について説明します。
洞調律 SR sinus rhythm
洞調律とは、心臓の正常なリズムのことで、右心房にある「洞結節」から発生する刺激が規則正しく心臓全体に伝わり、心臓が一定のリズムで拍動する状態を指します。
心電図所見
心拍数50~100/分
QRSの前に規則的にP波が出現
ⅠⅡaVF・V4〜V6でP波陽性、aVRでP波陰性
V1では二相性(±)となることが多い
各P波に1つのQRS波が対応する(=房室伝導が正常)
P波の電気軸は+15°〜+75°(または 0°〜+90°)の範囲になる
洞調律に含まれるもの
正常洞調律、洞性頻脈、洞性徐脈、洞性不整脈
正常洞調律 NSR normal sinus rhythm
心電図所見:
洞調律に加え、以下の条件を満たす
①P波とQRSが1対1対応
②HRが50(60)~100/分
③PP間隔とRR間隔がほぼ一定で、その変動幅は0.16秒以内
④P波正常(幅、高さ)
⑤PR時間正常
⑥QRS正常(幅、高さ)
⑦他の波形に異常がない
※洞性徐脈、洞性頻脈、洞性不整脈、房室ブロックではないことをイメージする
洞性頻脈 ST sinus tachycardia
洞結節の刺激発生が増えて頻脈になります。
刺激は正常の伝導路を通るため正常のP-QRS波形になります。

心電図所見:
①ⅠⅡaVF・V3~V6でP波が陽性
②HRが100/分以上
特徴:発作性上室性頻拍(PSVT)は急激にHRが増加するのに対し、洞性頻脈では徐々にHRが増加します。
肺塞栓症、甲状腺機能亢進症など
鑑別:発作性上室性頻拍(PSVT)、心房頻拍(AT)
治療:原疾患がある場合はその治療を優先します。頻脈によって心臓に負荷がかかる場合はβ遮断薬を使用します。(例:プロプラノロール[インデラル®]、アテノロール[テノーミン®]など)。
※参考 洞性頻脈をHRで鑑別する目安
一般的に洞性頻脈の最大心拍数は[220ー年齢]とされています。
例えば70歳の人のHRが150/分を超える場合、洞性頻脈の可能性は低いと考えられる。
洞性徐脈 SB sinus bradycardia
洞結節の刺激発生が減り徐脈になります。
刺激は正常の伝導路を通るため正常のP-QRS波形になります。

心電図所見:
①ⅠⅡaVF・V2~V6でP波が陽性
②HRが50(60)/分未満
原因:副交感神経の緊張、甲状腺機能低下症、高カリウム血症、低体温、薬剤、スポーツ心臓など
鑑別:洞房ブロック、房室ブロック
治療:徐脈によって血圧低下を伴う場合には硫酸アトロピンの投与。
洞性不整脈 SA sinus arrhythmia
若年者や迷走神経緊張状態では刺激発生の変化が起こります。呼吸性の洞性不整脈が多いです。(吸気時にHRは速くなり、呼気時にHRは遅くなります)
通常、最大RR間隔と最小RR間隔の差が0.16秒以上あるときに洞性不整脈とされます。
HR<70/分のことが多い。

心電図所見:
①ⅠⅡaVF・V2~V6でP波が陽性
②PP(RR)間隔が不規則…最大PP間隔ー最小PP間隔が0.16秒以上
原因:呼吸性(吸気と呼気に伴う変化)、ストレス、若年者
鑑別:PAC、房室ブロック
洞不全症候群 SSS sick sinus syndrome
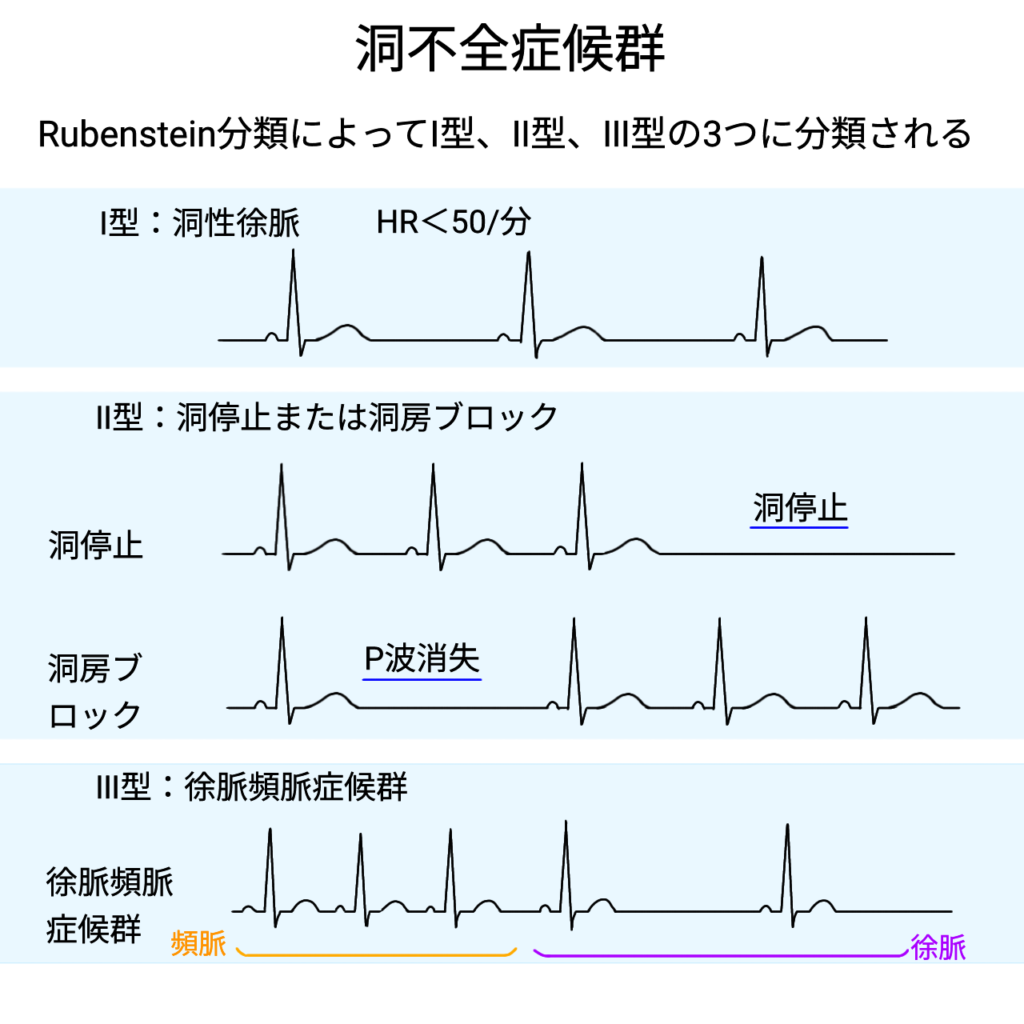
洞結節の機能が低下し、刺激発生がが現象して不規則になります。これにより、洞性徐脈、洞停止、洞房ブロック、徐脈頻脈症候群を生じます。
P波とQRSは基本的には正常だが、先行するP波が欠如する場合がある。
3つのタイプに分類されます。
I型…洞性徐脈
II型…洞停止、洞房ブロック
III型…徐脈頻脈症候群(bradycardia-tachycardia syndrome)
PSVT、AFL、AFが合併することも。
予後は比較的良好。
めまいや失神を繰り返す場合はペースメーカーの植込みが適応されます。
Adams Stokes発作
概要:徐脈により心拍出量が減少し、一過性の脳虚血を引き起こします。めまい、痙攣、失神を生じます。
不整脈はなかなか分かりづらいですよね。
分かりやすい説明を心がけます。
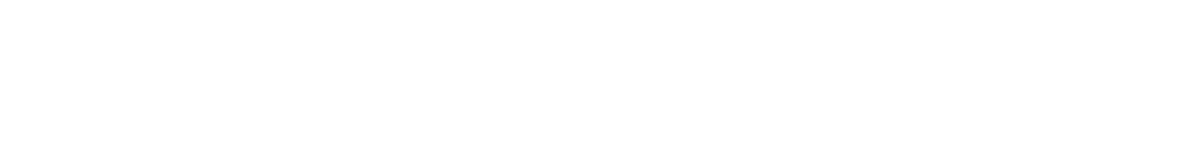



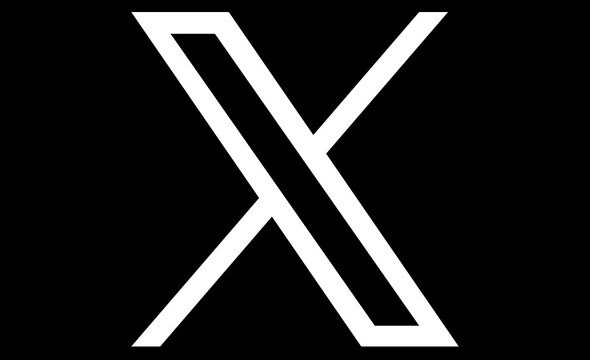
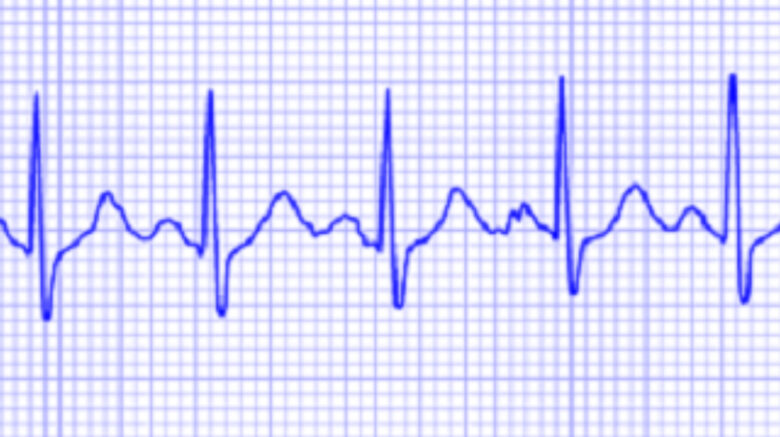

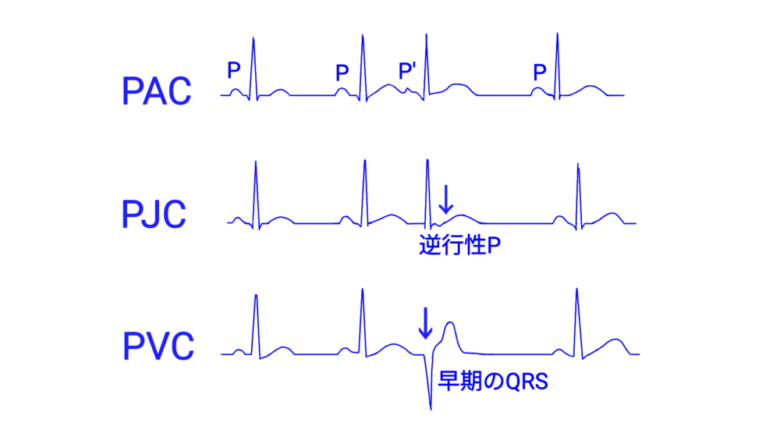
コメント