不整脈3回目は発作性上室性頻拍、心房頻拍です。
発作性上室性頻拍 PSVT SVT
発作性上室性頻拍 (PSVT,paroxysmal supraventricular tachycardia)の分類
1.房室回帰性頻拍 (AVRT,atrioventricular reciprocating tachycardia)
2.房室結節リエントリー性頻拍 (AVNRT,atrioventricular nodal reentrant tachycardia)
3.洞結節リエントリー性頻拍 (SNRT,sinus nodal reentrant tachycardia)
4.心房頻拍(異所性心房頻拍) (AT,atrial tachycardia)
5.心房内リエントリー性頻拍(心房内リエントリー) (IART,intraatrial reentrant tachycardia)
※PSVTの割合:AVRT約40%、AVNRT約50%、AT約10% SNRTまれ
ATとPSVTは区別されることも多い。
発生場所と原因:
心房内や房室接合部で約150~200/分で刺激が発生。
原因の多くはリエントリー。
鑑別:ST、AFLなど
※PSVTとSTのHRでの鑑別方法
PSVT…目安 HR150~200/分 ST…目安 HR100~180/分
STのHRは[220-年齢]以下のことが多い。
※PSVTとAT、AFLの鑑別方法
アデノシン三リン酸(ATP、一般名:アデホス)の静注を行います
ATPは一過性(10秒程度)に房室ブロックを起こすため、
◦PSVTの場合、100%停止します
◦それ以外は停止せずP波のみ現れます
規則正しいP波→AT
鋸歯状のP波→AFL
ATP静注により頻拍の鑑別ができ、PSVTでは治療になります。
PSVTの特効薬:
アデノシン三リン酸 (ATP、一般名:アデホス-Lコーワ アデホス)…静注のみ
ベラパミル(一般名ワソラン)…静注または内服
PSVTの発作予防:
ベラパミル(ワソラン)などのCa拮抗薬、ジソピラミド(リスモダン)などの抗不整脈薬Ⅰa群
房室回帰性頻拍 AVRT
房室回帰性頻拍 AVRT atrioventricular reciprocating tachycardia
Kent束・心房・房室結節・心室の旋回経路があり頻拍発作を生じます。
順方向性(正方向性)房室回帰性頻拍 (ORT,orthodromic AVRT)
AVRTの約90%は順方向性AVRTです。
刺激は房室結節を順方向(心房→心室方向)に伝わり、Kent束を逆方向(心室→心房方向)に伝わります。
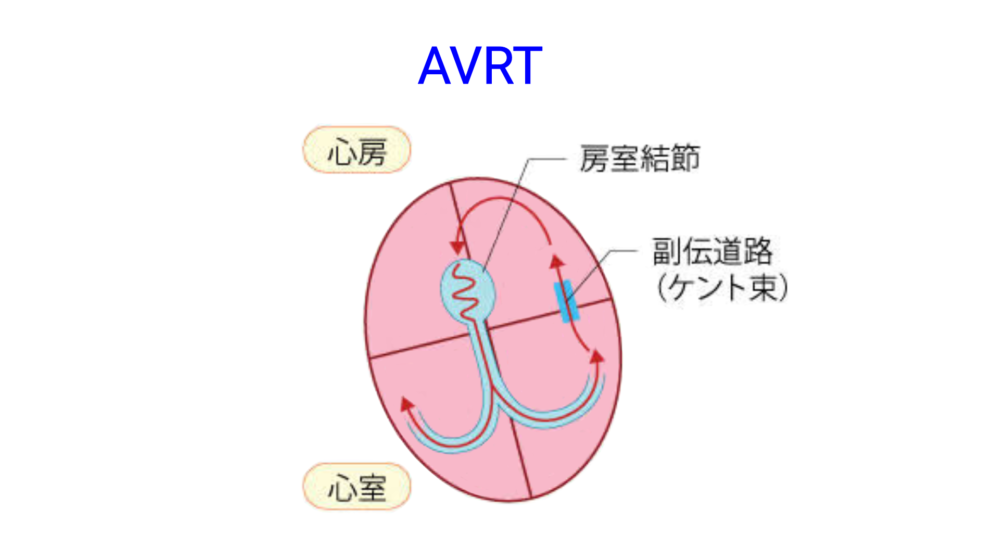
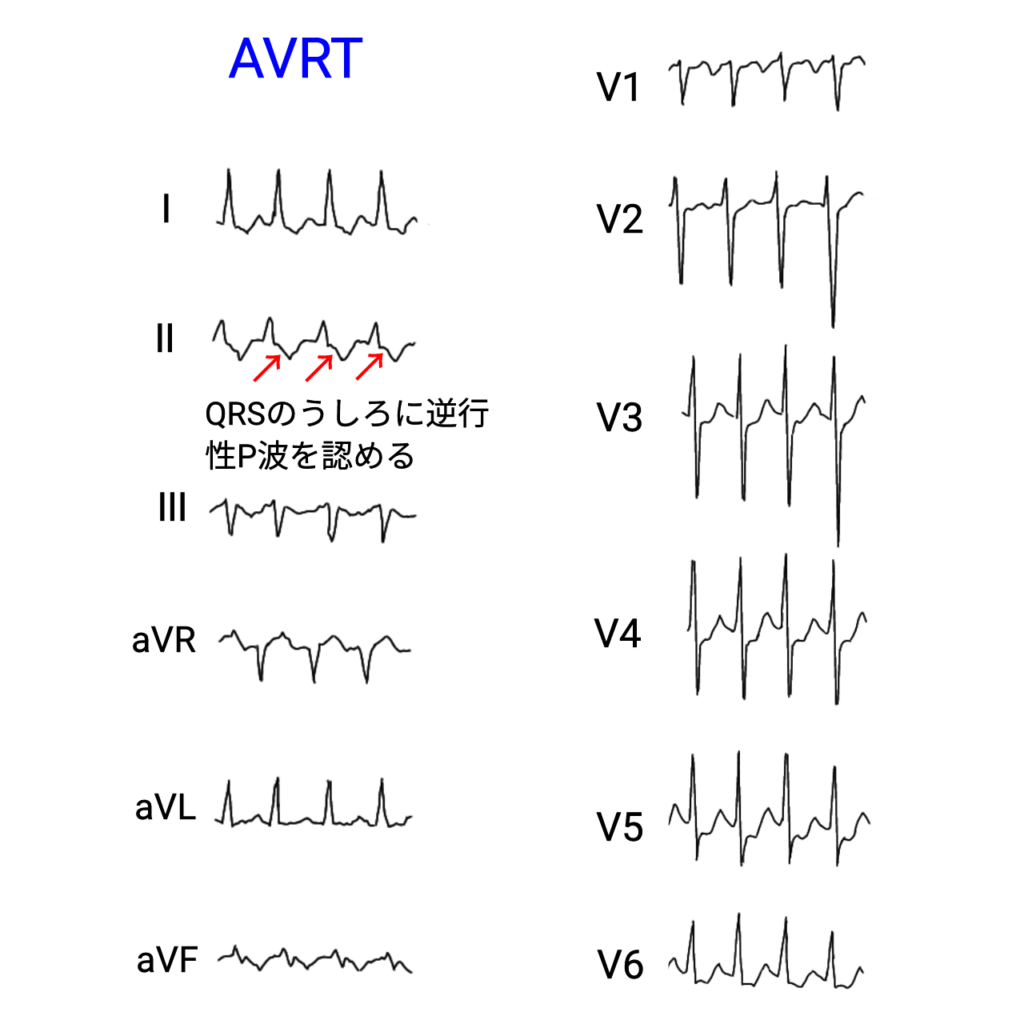
心電図所見:
1.HRは約150~220/分
2.narrow QRS regular tachycardia
3.ⅡⅢaVF誘導で逆行性P波(陰性P波)がQRSの直後に認められる ※逆行性P波と判断しづらいものも多い
4.RR間隔は一定
原因:Kent束(WPW症候群)
鑑別:AVNRT、ST、AT、AFL
治療:
薬物療法…ATP静注、β遮断薬(プロプラノロール、アテノロール)、Ca拮抗薬(ベラパミル、ジルチアゼム)、Ⅰc群抗不整脈薬(プロパフェノン、フレカイニド)内服
カテーテルアブレーション
逆方向性房室回帰性頻拍 (ART,antidromic AVRT)
AVRTの約10%は逆方向性AVRTです。
順方向性とは逆に、刺激が伝わります。
心電図所見:
①HRは約150~250/分
②wide QRS regular tachycardia
③デルタ波を生じる
④RR間隔は一定
原因:Kent束(WPW症候群)
鑑別:VT、変行伝導を伴う上室性頻拍など
治療:
薬物療法…ATP静注、β遮断薬(プロプラノロール、アテノロール)、Ca拮抗薬(ベラパミル、ジルチアゼム)、Ⅰc群抗不整脈薬(プロパフェノン、フレカイニド)内服
カテーテルアブレーション
房室結節リエントリー性頻拍 (AVNRT, atrioventricular nodal reentrant tachycardia)
房室結節リエントリー性頻拍 AVNRT
約80%はcommon type(通常型)、約20%はuncommon type(非通常型)
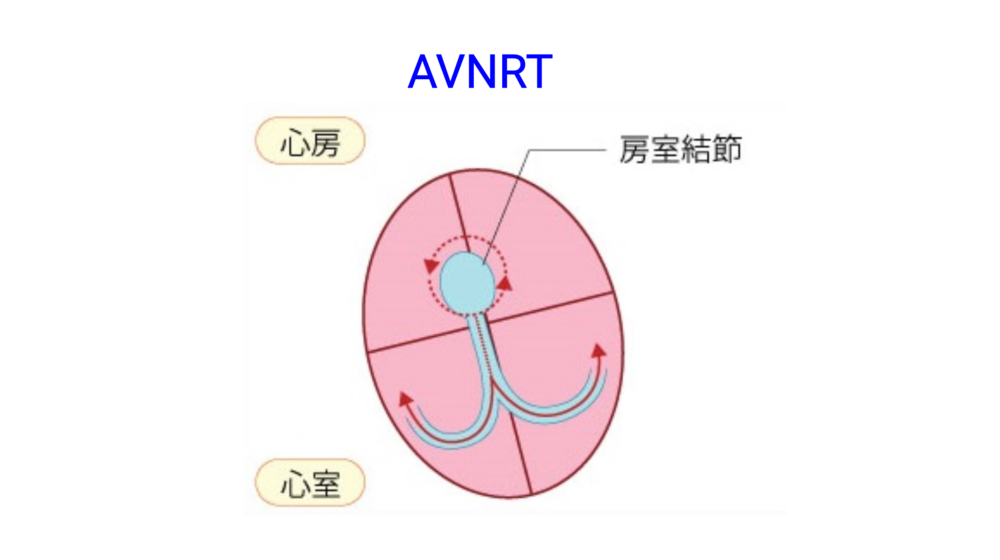
ⅰ)common type(通常型) AVNRT (slow/fast)
slow pathwayを順行性に、fast pathwayを逆行性に伝導します。
突然発症し、突然停止します。
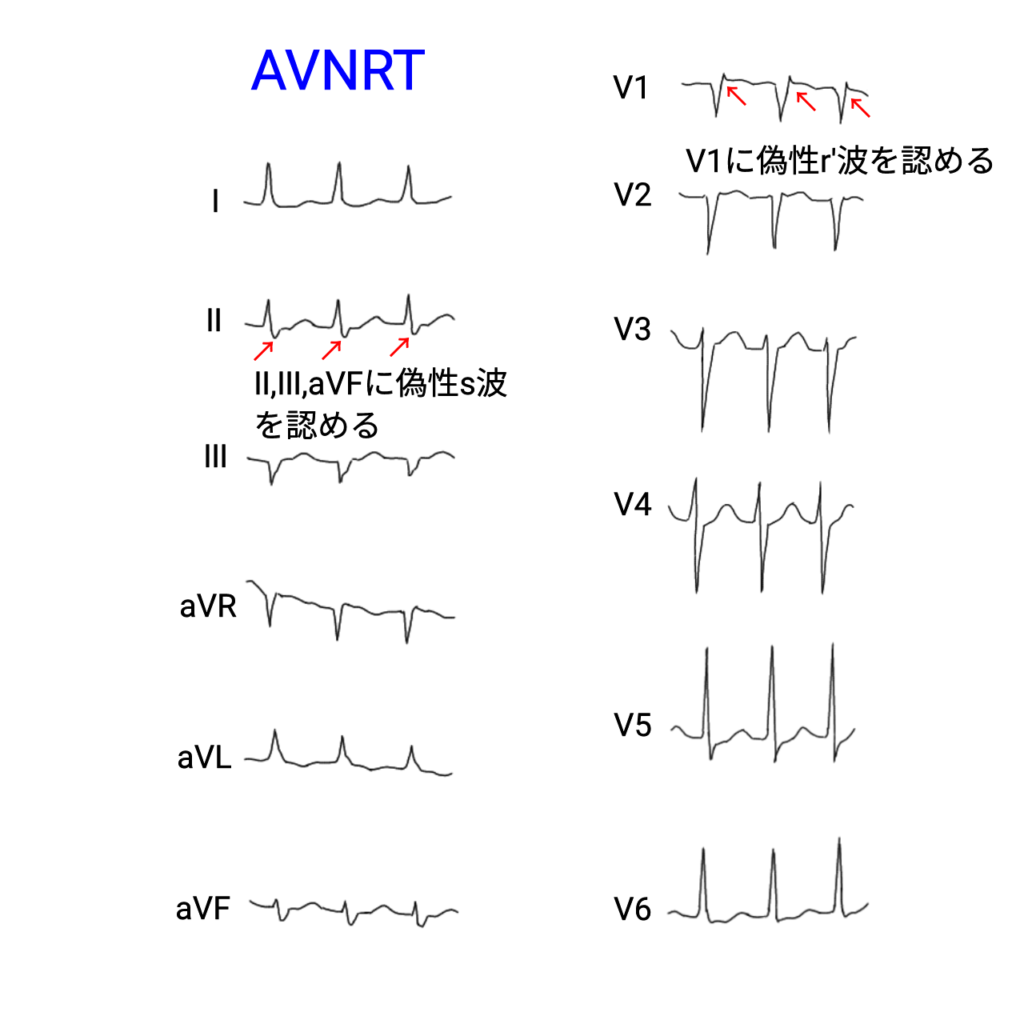
心電図所見:
1.HRは約150~200/分
2.narrow QRS regular tachycardia
3.short RP’ tachycardia(P’R>RP’)
Ⅱ、Ⅲ、aVFで異所性P波(P´波)は、
約半数でQRSに重なりはっきりしない。
約半数で偽性s波としてみられる。
まれに偽性q波としてみられることがある。
V1で偽性r´波としてみられる。
ⅱ) uncommon type(非通常型) AVNRT (fast/slow)
心電図所見:
1.narrow QRS regular tachycardia
2.異所性P波(P´波)はlong RP´ tachycardia(P´R<RP´)
ⅲ) uncommon type(非通常型) AVNRT (slow/slow)
心電図所見:
①narrow QRS regular tachycardia
②異所性P波(P´波)はshort RP´ tachycardia(P´R>RP´)
原因:房室結節二重伝導路(遅伝導路-速伝導路間のリエントリー)による
鑑別:AVRT、ST、AT、AFL
治療:カテーテルアブレーション(根治率は95%以上)
☆房室回帰性頻拍AVRTと房室結節リエントリー性頻拍AVNRTとの鑑別方法!
ORTはⅡ、Ⅲ、aVF誘導でQRSの直後にP´波(陰性P波)がみられます。
ARTはwide QRSで通常、デルタ波が見られます。
common type AVNRTはⅡ、Ⅲ、aVF誘導で
1.P´波がQRSと重なり見えない場合(多い)
2.偽性q波が出る場合(まれ)
3.偽性s波が出る場合、V1で偽性r´波が出る場合がある
uncommon type AVNRT(まれ)はT波の後にP´波(陰性P波)を生じ、longRP´ tachycardiaの形態になります。
AVRTはaVRでSTが上昇しやすい。※覚え方 AVRTはaVRでST上昇!←AVRが共通!
洞結節リエントリー性頻拍 (SNRT,sinus nodal reentrant tachycardia)
洞結節リエントリー性頻拍 SNRT
ATに含める場合あり! まれな疾患
突然発症し、突然消失する
心電図所見:
1.HR100~150/分
2.RR間隔は一定
3.異所性P波(P´波)は洞調律のP波と同一=P波は正常
4.P´R時間はさまざま
原因:洞結節と周囲の心房筋の間でのリエントリー、心臓手術後など
鑑別:洞性頻脈、2:1伝導性のAFL、AT
心室内変行伝導を伴うPSVT
平常時に伝導障害(脚ブロック)がなくても、頻拍により不応期の関係で心室内変行伝導(右脚ブロック型、左脚ブロック型)となることがあります。
右脚ブロック、右軸偏位になりやすいのは、右脚の不応期が左脚より長いためです。これは機能的ブロックと呼ばれ、病的意義はありません。
脚ブロックを伴うPSVT wide QRS
右脚(左脚)ブロックにPSVTが合併したもの
3.5mm(0.14秒)以上のwide QRS regular tachycardiaであり、心室内変行伝導を伴うPSVTやVTとの鑑別が必要。
頻拍となり、右脚または左脚の不応期よりも頻拍周期が短くなると、それぞれ右脚ブロック、左脚ブロックとなります。右脚の不応期は長いため右脚ブロック型が多いです。
鑑別:VT (VTと脚ブロックを伴うPSVTとの鑑別は困難なことがあります。)
治療:迷走神経刺激、ATP(アデノシン三リン酸)5~20mg静注。鑑別が困難な場合は直流通電を行います。
心房頻拍(AT atrial tachycardia)と房室接合部頻拍(JT junctional tachycardia)
心房頻拍(AT)…心房で刺激が発生します
房室接合部頻拍(JT)…房室接合部(主にHis束)で刺激が発生します
ATとJTの鑑別にはP波の形やPR時間を見ます。
PSVTとVTの鑑別方法
◦QRS幅 QRS幅が0.16秒以上ならばほぼVTと診断
◦房室解離 R rate<P rateなら房室解離がありVTと診断
◦心室捕捉(捕捉収縮) (ventricular) capture beat wideQRSの間に洞調律があればVTと診断
◦融合収縮 洞調律とVTの融合が見られたらVT
◦左軸偏位(-30°~-90°)、北西軸(-90°~-180°)であればVTの可能性が高い
◦脚ブロックの形 通常の脚ブロック波形と異なり、変形している場合、VTの可能性が高い
◦V1での下りカーブ 左脚ブロック型の場合、r波からS波への下りカーブが緩やかであるとVTの可能性が高い
◦洞調律時の波形
右脚ブロック型や左脚ブロック型となりQRSの立ち上がりは鋭い。一方でVTの多くはQRSの立ち上がりは鋭くないです。
右脚ブロック型は鋭いR波があるため上室性と診断しやすい。左脚ブロック型はwide QRS となります。
V1、V6で脚ブロックの形が崩れているならVTの可能性が高い。(PSVTでは典型的な脚ブロックの形になります。)
房室解離や心室捕捉があればVTと診断できます。P波があれば房室解離があります。
血行動態が保たれているwide QRSの頻拍にはATPを投与します。ATP投与後に洞調律に戻れば発作性上室性頻拍と判定できます。
心房頻拍 (AT,atrial tachycardia)=発作性心房頻拍 (PAT ,paroxysmal atrial tachycardia)
心房頻拍 AT
心房頻拍には洞結節リエントリー型、心房内リエントリー型、心房自動能亢進型があります。
1)単源性心房頻拍、多源性心房頻拍 (MAT,multifocal atrial tachycardia)
2)房室伝導比一定のAT、房室伝導比不定のAT
心房で異所性刺激が発生し、頻拍が生じます。
心房拍数は100~250/分、HRは100~200/分
⇐明らかな粗動波が見られても、粗動波数が250/分未満ならATと分類されます。
HRは80~90/分になることもあります。
刺激発生部位が洞結節に近い場合、洞性頻脈 や洞調律 と紛らわしいことがあります。
ATとSTの鑑別方法は、P波の形の違いを見ることです。発作時のホルター心電図や12誘導心電図を詳細に見なることで判別できます。
なかには、ATと診断されず心療内科に紹介されることもあります。
心電図所見:
1.洞調律と異なる形のP´波(異所性P波)が出現
2.QRS数<P´波数
3.P´R時間は計測不能のことが多い
4.RR間隔は一定または不定
narrow QRS regular tachycardiaとnarrow QRS irregular tachycardiaがある
⑤QRS幅<0.10秒
※多源性心房調律や多源性心房性期外収縮3連発以上がHR100/分以上になるとMATと診断されます!
鑑別:SR、ST、AFL、AF
治療:
薬剤(リエントリーによるATにはⅠa群やⅠc群抗不整脈薬、自動能の亢進によるATにはβ遮断薬)
カテーテルアブレーション(根治率90%以上)
PAT(AT) with block
⇒房室ブロックを伴ったPAT(AT)
心房拍数が多くなると(例 心房拍数200/分以上)、刺激が全て心室に伝わらず房室ブロックを生じます。伝導比は様々です。
Wenckebach周期(徐々にPR間隔が延長してQRSが脱落する)となることもあります。
ジギタリス中毒でみられやすい。
2:1伝導のAT
⇒2:1房室ブロックを伴ったAT
例えばP波が180/分、QRSが90/分出現するものをいいます。
鑑別 ST、AFL、AF、2:1AVB
多源性心房頻拍 MAT
多源性心房頻拍 MAT multifocal atrial tachycardia
心房内の複数で異所性自動能の亢進が起こります。
発症の背景に慢性肺疾患などがあります。
心電図所見:
1.3種類以上のP波がある
2.RR間隔は不整
COPDなどの肺疾患が基礎にあることが多い
房室接合部頻拍 JT junctional tachycardia
まれな疾患
鑑別:AVNRT、ST
皆さん、今日もお疲れ様でした。
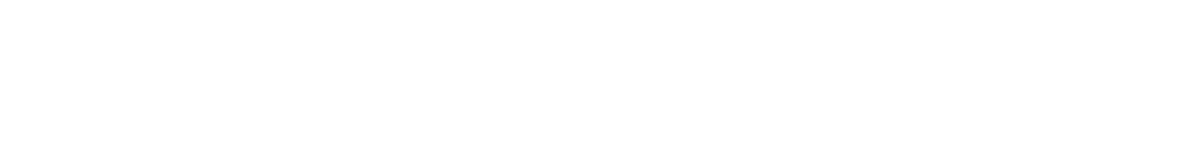



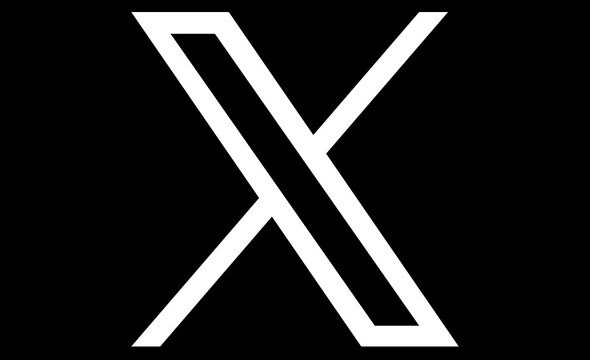
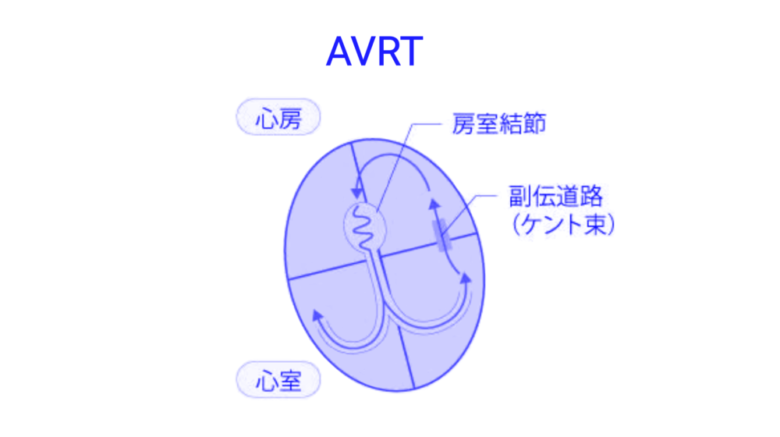
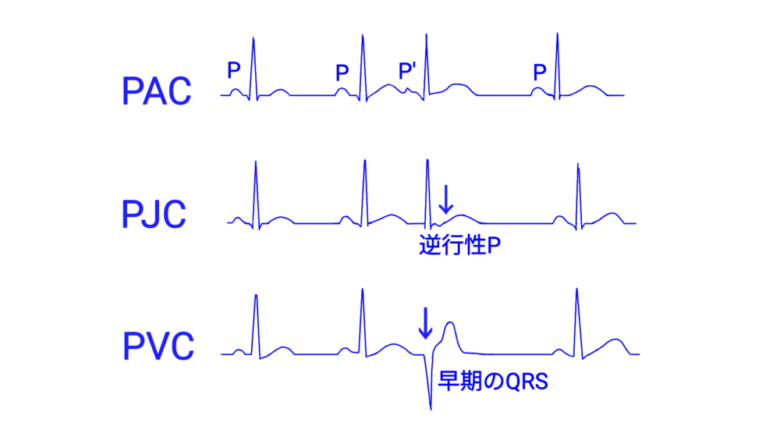
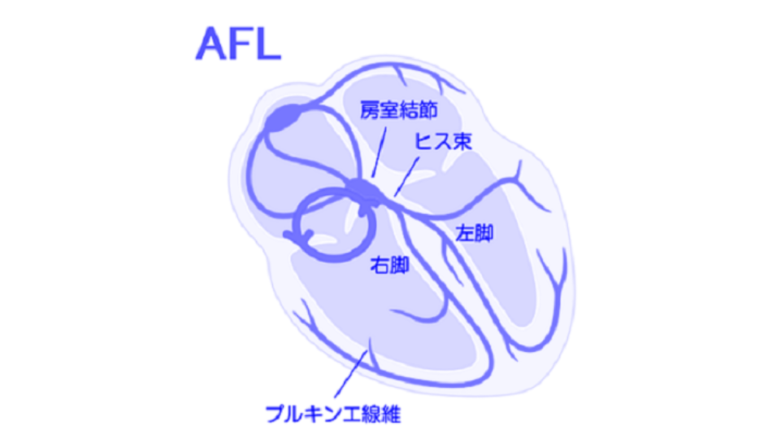
コメント